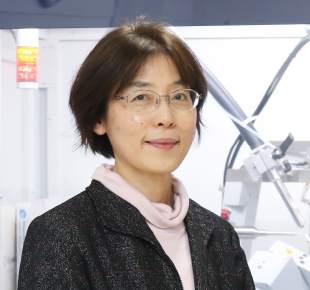「ソフトクリスタル」という
新たな学術分野を開拓。
生命環境学部 環境応用化学科 ※2021年4月誕生
加藤 昌子 教授
「結晶」と言えば、水晶やダイヤモンドのように硬くて安定な物質というイメージがありますが、そんな常識を覆す結晶が、近年、相次いで発見されています。結晶の三次元秩序構造を保ちながら、「こする」「蒸気にさらす」といった弱い刺激を与えると、柔軟な構造変化を起こして光を発したり、色が変わったり…。私たちの研究グループでは、そうした性質をもつ結晶を「ソフトクリスタル」と命名。これまで現象論にとどまっていたこの分野の研究を新しい学術領域として高めていく研究組織を立ち上げ、私はその代表を務めています。ソフトクリスタルのしくみを解明し、発光の制御や自由な合成の実現、新機能の創出など、将来のイノベーションにつながる成果を引き出します。

例えば発光性のソフトクリスタルを布地に織り込めば、電子デバイスを一切使わずに、布地そのものから鮮やかで美しい光を発することが可能に。さらに温度変化や機械的刺激によって光の「ON/OFF」や色の変化を自在にコントロールする技術が確立されれば、情報通信や産業、エンターテインメントなど、多彩な分野での活用が見込まれます。
原点は、実験を心から
楽しく感じていた学生時代。
わずかな偶然+好奇心から、
世界的な研究がスタート。
私たちの研究組織では、化学・理論計算・数物・工学分野の研究者が連携し、「ソフトクリスタル」という新たな学術分野の開拓に挑戦しています。パイオニアとしての道のりは決して平坦とは言えませんが、私自身はこの研究をとても楽しいと感じてきました。もちろん「社会に貢献できる成果を出したい」といった想いもありますが、それ以上に自らの好奇心が支えになっていると思います。
私のもともとの専門分野は、発光性の金属錯体。実験でさまざまな色の光を見て「きれいだな」と感動した学生時代が、私の原点かもしれません。育児との両立に苦心した時期も、研究をやめようとは考えませんでした。その頃に勤務していた大学の研究室でのことです。放ったままにしておいた白金錯体が、ある時、光り出しました。「なぜ?」と不思議に思い、原因をいろいろ探っていくうちに「これは世界的にも大きな成果を出せるかも!」となって…。そこから、「ソフトクリスタル」の研究が始まりました。きっかけは、偶然の産物と、それを見逃さずに面白がって突き詰めようとする好奇心だったのです。
科学者には知識や技術に加え、
センスも必要。
関西(カンセイ)で
感性(カンセイ)を磨こう!
研究室のスローガンは「関西(カンセイ)で感性(カンセイ)を磨く」です。理系の学生にとって感性という言葉は縁遠いイメージがあるかもしれませんが、科学の道を究めていくうえで科学的センスは欠かせません。例えば偶然の産物に対して、そこから成果につながる何かを見つけられる人と見つけられない人がいますが、その差は技術だけではなくセンス、感性なんです。そういった感性を磨くには、まず知識が欠かせませんし、さらに知識を「ただ知っている」というだけに留めず、自分で実際に手を動かして知識を経験へとつなげることが重要。また視野を広げ、いろいろな角度から物事を見て考えるといったことも心がけてほしい。それらの積み重ねで、感性は磨かれます。
「面白がる」というのも大事ですね。私自身も好奇心に突き動かされるように研究を繰り広げてきました。若い人たちにも楽しんで研究に取り組んでもらい、そこから生まれる新しい発想でさらなる未来を切り拓いてほしいと願っています。