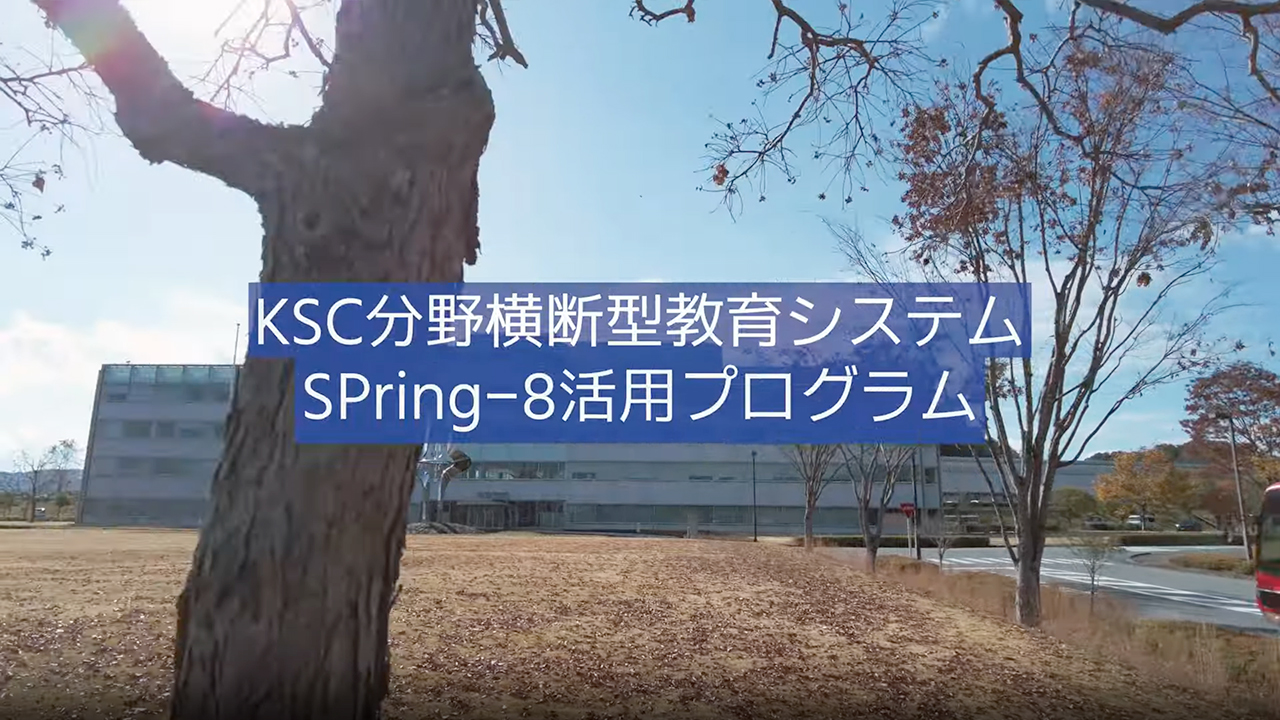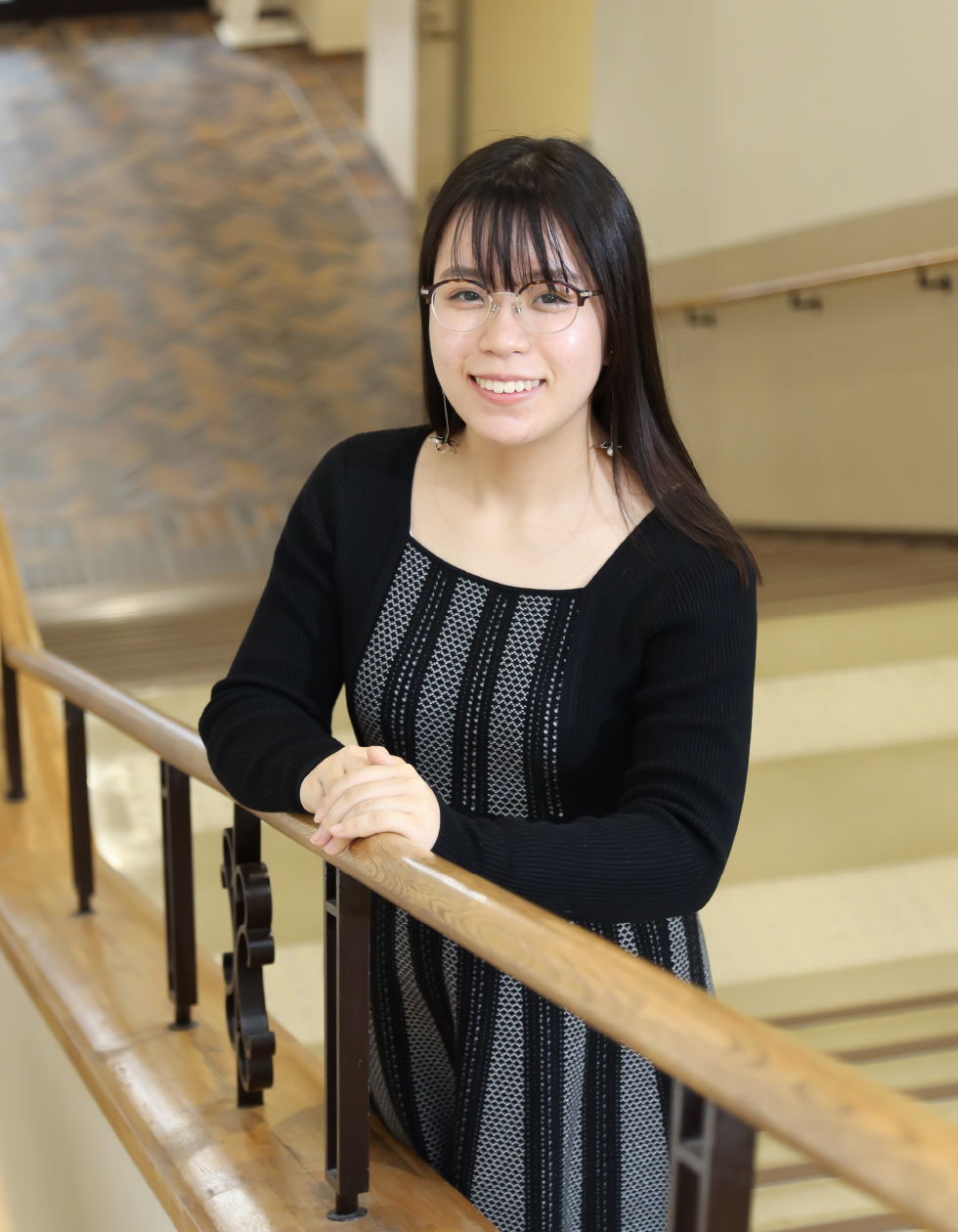
憧れの世界3大放射光施設
「SPring-8」等での
実習で大きく成長!
理工学部 先進エネルギーナノ工学科 2年生
※取材当時
宍戸 優希 さん
「地震などの災害から人を守れる物を作りたい」という想いを抱き、関学の理工学部に入学。まだ2年生ですが、さまざまな授業やプログラムを通じてたくさんの気づきを得て、視野を大きく広げることができています。例えば世界でも屈指の大型放射光施設『SPring-8』で実験を行う授業。最先端装置を駆使して半導体が作られる工程を間近で見るなど、学内ではできない大規模な実験や解析をいろいろ体験し、強い刺激を受けました。また『AI活用人材育成プログラム』では、自らの研究にAI(人工知能)を活用する方法などについて学んでいます。英語力を高めるため、3年次以降には留学も実現したい。めざす未来に向け、いま、希望通りの学びができていると実感しています。

「授業やプログラムを通じて、多くの友人ができたのもうれしい」と宍戸さん。同じ学科の友人たちとお茶を飲みながら授業やテストについて話したり、課外プログラムの『焚火Talk』で仲良くなった友人と遊びに行ったり。授業の実験で知り合った同学科の先輩には進路相談も。勉強で気を張る毎日のなかで、そうした交流がいい息抜きとなり、心の支えにもなっています。
多くの気づきや発見が
得られる実験科目が大好き。
『SPring-8』での実験では、
院生からも刺激を。
普段の授業では、実験科目が特に面白いと感じています。座学で学んだ知識について自分の目で再確認でき、また流体力学など座学で履修していない科目の実験を行う機会があるのもいいですね。特に印象に残っているのは「自分たちの感覚では“さらさら”の水でも、計測すると“ねばねば”とした粘性が数値に示される」という実験です。定量化した数値で表される物理の世界は、人間の感覚とは違っているんだと実感しました。
世界最高峰の研究施設の一つである『SPring-8』での授業では、大規模なX線装置などを用いた実験ができました。予想通りの結果が得られないこともありましたが、原因についてその場で教授や院生の方々とディスカッションができたのが刺激的でしたね。院生が『SPring-8』の最先端設備を自分たちの研究にどのように活用しているかがイメージでき、私自身の今後の研究活動に向け、とても有意義な時間が過ごせました。何より、高校生の頃からの憧れの施設だった『SPring-8』に行けたという事実が、一番うれしかったですね。
怖いイメージがあったAIも、
今や「頼れる相棒」に。
理系の視点を養えば、
世界の見え方が変わっていく。
高校生の頃、AIと言えばスマホの音声アシスタントか、「シンギュラリティが起きてAIが暴走する」といったSF小説の怖いイメージを抱いていました。しかしAI活用人材育成プログラムでAIについて正しく学び、今は「高度な計算をアシストしてくれる相棒」と感じています。さらに学びを深め、自分の研究結果の解析にAIを活用できるようにしたいですね。
大学で学んで、世界の見え方が変わりました。学科の授業で学んだ内容がスマートフォンなど身近な機器に使われていたり、ニュースで知った社会問題へもこの最先端の研究内容を用いると解決できるのでは、といったことを普段から意識する、理系ならではの視点が養われています。また、「理系=研究」という偏った印象を持っていましたが、『SPring-8』の授業や、AI活用人材育成プログラム』で学ぶことで、研究で得た成果をどのように社会に役立てるのか、までを考えるようになり、自分の目標や未来の可能性は多様に広がったと実感しています。それをふまえ、今後の研究テーマを絞り込んでいきたい。まずは論文を書くうえで不可欠な英語力の修得をめざし、留学に挑戦することが直近の目標です。